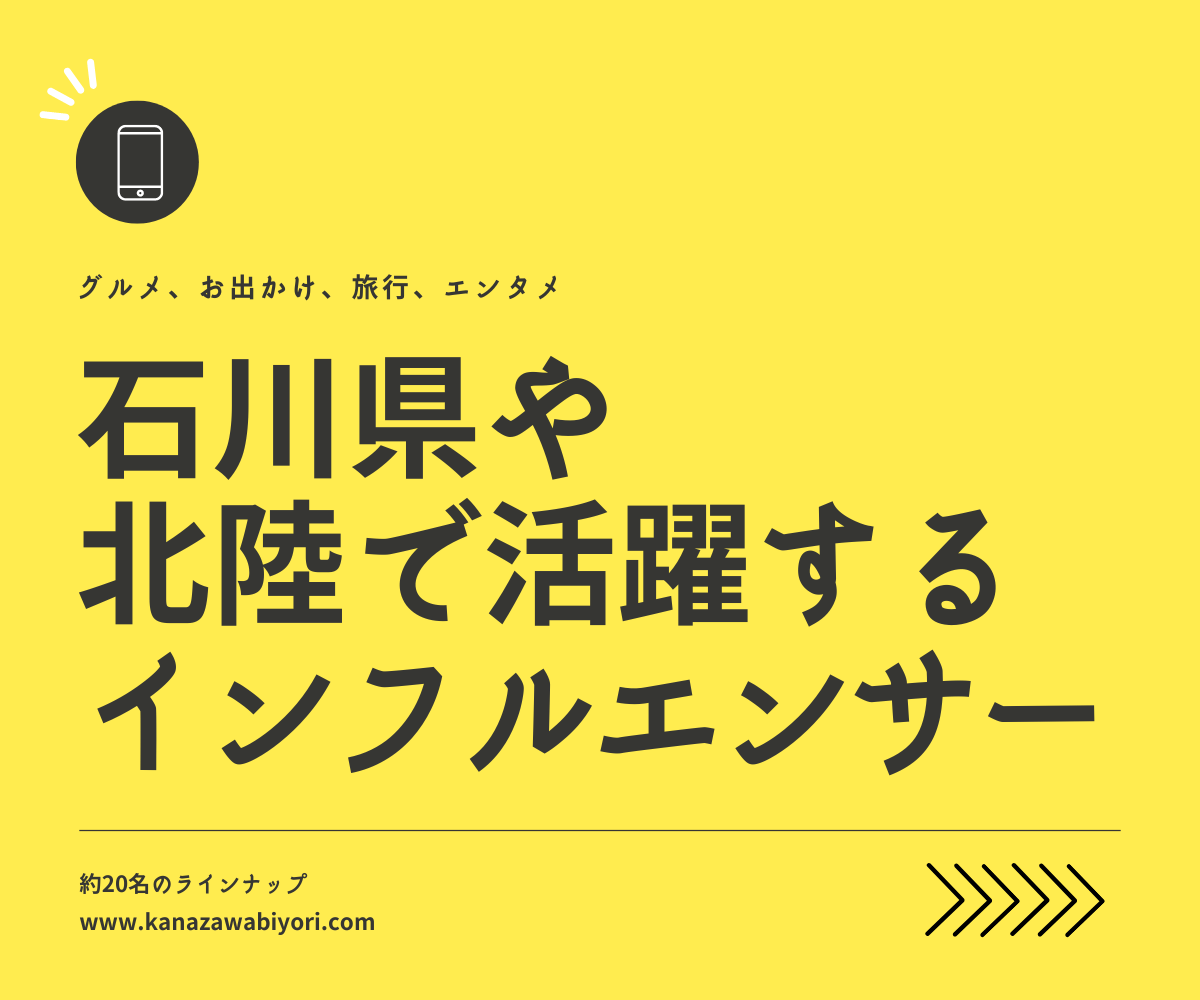第7回

いまから40年ほど前のこと。母親に連れられて銭湯に行くと、まずは下駄箱の「28」番へと真っ直ぐ向かい、「28」番が空いていればそれでよし、塞がっていれば「22」番、それも駄目なら「40」番に――というのが自分なりの決め事だった。脱衣場でも同じ手順でロッカーを確保するのだが、それは当時、とりたてて珍しくもない光景だったと思う。
かつて少年たちの一番のヒーローはプロ野球選手であり、下駄箱やロッカーの番号は彼らの背番号を指した。私にとってのヒーローは阪神タイガースの選手であり、優先順位をつけるなら江夏豊(背番号28)、田淵幸一(同22)、マイク・ラインバック(同40)の順。巨人ファンなら「1」番(もちろん王貞治)が最も競争率が高かったと思う。
いまでもたまに銭湯に行くと、つい下駄箱の前で数字を探してしまうが、銭湯といえば、こんな話もある。
全国の銭湯経営者には北陸出身、なかでも石川県出身が多い。特に関西ではその傾向が顕著で、大阪で6割、京都だと8割を占めるというから驚きだ。関東でも新潟に次いで多いという。
なぜ、こんなことが起きたのか?
一説には北陸の農家の次男、三男坊が都会へ出て銭湯に働き口を求め、やがて次々と暖簾分けしていったのではないかということ。銭湯の仕事はかなりの重労働だが、それも雪国の農作業に比べるとさほど苦でもなく、かように忍耐強い北陸の人間が歓迎されたというのだ。豆腐屋さんにも北陸出身者が多いそうで、これも同様の理由であるらしい。
また東京型銭湯の特徴であるタイル画(富士山が何といっても人気)の9割ほどは、九谷焼でできているとのこと。まだまだトピックスには事欠かないが、湯あたりしないうちに、今回はこのへんで。