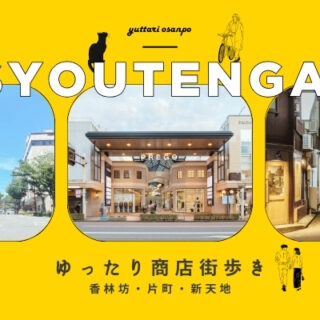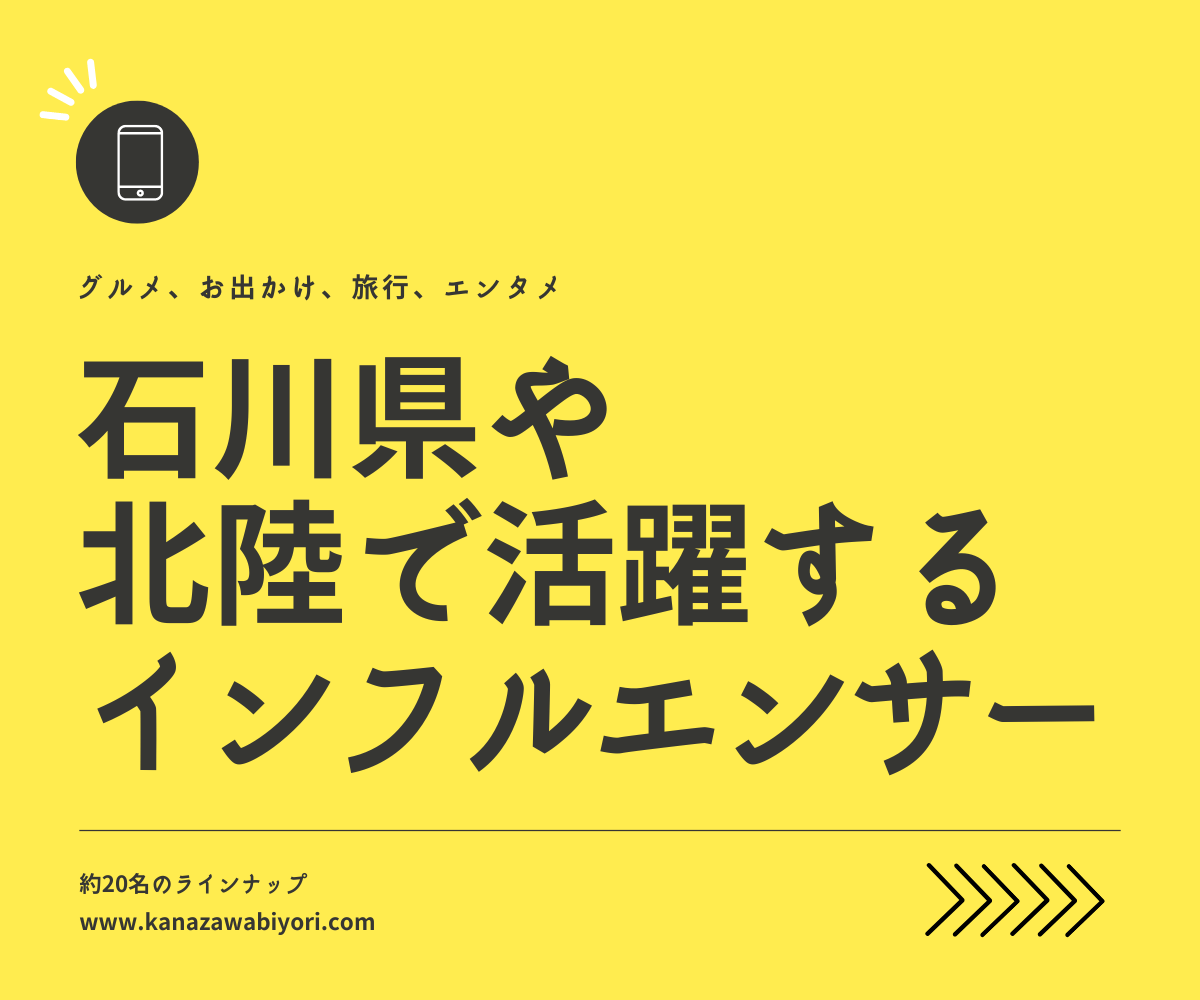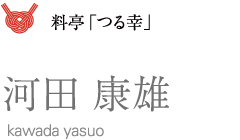
高校生の頃に、先代の志を受け継ぐ決意をする。金沢を代表する店であり続けることを自らに課し、日本料理の本質を究めるべく板場に立つ。

男と女は、厳然と異なる。
異なればこそ、雛の節句には、女の子に「やさしくなりなさい」と教え、端午の節句には、男の子に「雄々しくなりなさい」と教えるのである。
大阪の元女性知事は、かつて大相撲の土俵に上がりたいと要求して大方の失笑を買ったが、たしかに、そのことをもって男女同権の権利を主張していることになると考えるのは、はなはだ可笑しな話である。宝塚歌劇団に男性も入れよという主張が通るはずもあるまいに。
総理大臣や大学教授をめざすことと、大相撲の土俵に上がりたいということとは、同列に扱われるべき事由ではない。大相撲はいわば文化である。文化というものが本質的に持っている〈遊び心〉を深く理解するならば、こういう唐変木なことは決して言わぬものなのである。
料理は、男の世界である。
一椀の汁をつくるにも、万遍の優柔不断、万遍の逡巡があったのちに、それこそいのちを懸けたひとつまみの塩がくべられる。
すぐれた料理人のつくる料理が凄絶なまでに美しいのは、一汁一菜の端々にまで、いのちを削った覚悟がこめられているからである。
「そのように仰っていただくのは嬉しいのですが、最近の若い職人は、料理にいのちを懸けるということが皆目わからないようですね。辛抱どころか、ほんの数年で辞めてしまう子も大勢います。男らしくあれかしという気組みを失ってしまったんでしょうかね」
河田康雄は、いったん強く目を閉じたあと、大きな歎息をひとつ漏らす。
金沢の日本料理の名を全国に喧伝することにもっとも大きく寄与した料亭『つる幸』の開業は昭和四十年。先代河田三朗はまさに天才ともいうべき至芸で、修業の地で学んだ京料理のたおやかさに、金沢の骨太さを見事に融和させた。
二代目河田康雄もまた大阪の『味吉兆』で盆も正月もない七年間の修業をよく耐えた。
『つる幸』の板場をたばねて四年。先代の薫陶を十分に受け継ぎながらも、それだけではない料理に日々工夫を凝らして、若々しさがあふれる中にも、最近は、二代目ならではの力強さがいっそう極まってきたと評判である。
日本人の美意識というのは、生々流転にある。完成された美ではなく、つねに揺れ動き、つねにたゆたう、不確かで、曖昧模糊とした生命に自らの魂を重ね合わすところに私たちはひそとした感動を見出す。
料理は、その日その日の食材、天候、体調にことごとく左右される。このようにやるは、決してこのようにやるほかないということではない。まさに、一日一日が勝負である。
朝目覚めた瞬間から、板場を綺麗に洗い清める仕舞いまで、料理人は片時も息を休められない。
「こういうことを言ってはなんですが、肩、腰の凝りが段々とひどくなってきましてね。時々、自分は本当に四十歳前なんだろうかと疑うこともあります」
そう言って苦笑するが、無論、『つる幸』を継いだことを悔いているわけではない。これほど気の張る毎日をおくれることは、望外の幸せでもあると感じている。だが、しかし、完結するということがない職業であるだけに、そうした緊張の連続に、ときに気持が軋むこともたしかなのだ。
「楽しみですか? お客様の満足する顔と言いたいところですが、次回はどうだろうと考えると、楽しみよりもむしろ不安が頭をもたげることもありますしね。やっぱり温泉かな。いやいや、たいそうな温泉でなくともいいんです。町中の湯にどぼりとつかり、手と足を伸ばしているときが、一番楽しいといえば楽しいのかな」
河田康雄。三十七歳。
金沢の日本料理を担うに相応しい、いい男、である。
筆者プロフィール
正岡順
エッセイスト。金沢市在住。料理、温泉、ホテルなどについて一家言あり。
- TEL