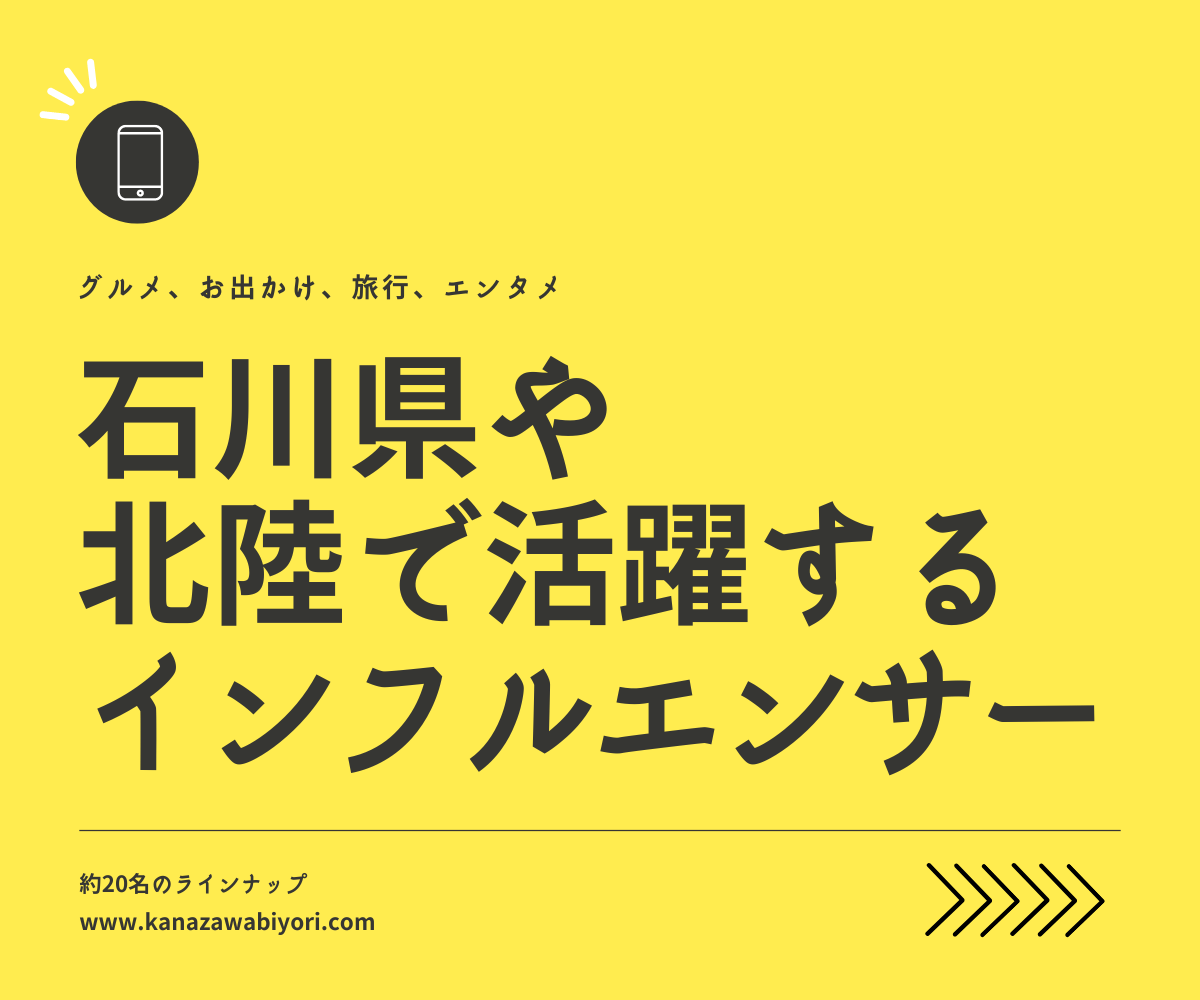【蓮だより】加賀れんこんをさらなる高みへ。河北潟の農家が挑む、オンリーワンの付加価値づくり
2024年3月14日(木) | テーマ/エトセトラ

〈 農援ラボとは… 〉
地元の農産物にこだわる飲食店や、未来の農業の担い手など、WEBを通じて北陸の農業と食への探求を情報発信することで、北陸の農と食を応援するオンラインメディアです。
「実はいま、れんこん由来の成分を配合した化粧品を共同開発しています。れんこんにはポリフェノールが豊富に含まれていて、美白効果が期待できるんですよ」
小ぶりの容器に入ったサンプルを手にそう話すのは、農事組合法人「蓮だより」代表の川端崇文さん。れんこんの出荷準備に追われる作業場から目と鼻の先にある小さな事務所で、まさか化粧品が話題になるとは。しかしこれまでの川端さんの歩みを知る人から言わせれば、そうした試みも「想定の範囲内」といったところだろう。

蓮だよりの設立は2012年。加賀野菜の一つとして知られる加賀れんこんの生産・販売を目的に、川端さんが立ち上げた。「どろんこファーム」と名付けた蓮だよりの農地は、すべて河北潟の干拓地にある。石川県のほぼ中央、金沢市・かほく市・津幡町・内灘町にまたがるこの干拓地は、農地利用を前提として昭和時代に造成されたもの。平坦な土地に延々と畑が広がる光景は、実際に目にすると想像以上に壮観だ。
2006年に初めて干拓地に足を踏み入れた川端さんもまた、同じことを感じたに違いない。会社員生活に閉塞感を覚える中、「河北潟の広大な畑でぽつんと一人、胸まで水に浸かって収穫作業している姿に衝撃を覚えて」、川端さんは文字通り畑違いのれんこん農家の道へと飛び込んだ。

最初の数年間は周囲から教えられるがままにれんこんを栽培していた川端さんだったが、持ち前の探究心から、徐々に自分自身のやり方を取り入れるようになった。その一つが無農薬栽培。「自分が食べたいと思うものをつくりたい」と、化成肥料のみに頼らない天然肥料を用いた土づくりにも取り掛かった。
丹精込めてつくった川端さんのれんこんの評判は上々。ご年配の方からは「子どもの頃に食べた味だ」と嬉しい感想も寄せられた。しかし当時は生産者組合に属する立場で、自身のこだわりを消費者に直接届ける手段は限られていた。

そうしたジレンマを抱えていた川端さんの転機は、金沢のとあるフレンチレストランのシェフとの出会い。客として訪れた際にれんこん農家であることをシェフに打ち明けると、川端さんのれんこんに興味をもってくれたのだ。この初めての営業活動が実を結び、縁が縁を呼んで後に首都圏のレストランと取引するための素地が整った。
「東京ではれんこんといえば茨城県産。それまで加賀れんこんは北陸三県で出回るものだったんです」と川端さん。大きくて甘みの強い茨城のれんこんと比べ、加賀れんこんは小ぶりだが粘りが強いのが特徴。フレンチなど創作系の料理を得意とするシェフにその個性が面白がられ、手応えを感じた川端さんは、蓮だよりの設立へとかじを切ったのであった。

2022年には蓮だよりでつくる加賀れんこんを「川端れんこん」と命名。さらなるブランド化を図る。
「夏から秋・冬にかけて収穫されるれんこんは、その収穫時期によって味に違いがあります。夏れんこんは甘くてみずみずしく、秋・冬れんこんは糖分がでんぷん質に変換されることで粘りが出てくる。でもそれだけではなく、一つ一つの節もまた性質や味の特徴が違うんです。肉を部位ごとに分けて売るように、これまでは『れんこん』と一括りにされていたものを細分化することで、よりキメの細かい提案ができるようになると僕は考えています」

化粧品開発も、部位ごとの販売も、れんこんの廃棄ロスと付加価値の創出という二つの難題に実直に向き合ったからこそ生まれた発想だ。その一方で川端さんは、加賀れんこんが抱える潜在的な課題にも目を向ける。
「同じく加賀野菜の一つに数えられているさつまいもの五郎島金時は、品質による等級分けがなされていますが、加賀れんこんにはそうした基準がないのです。加賀れんこん全体のブランド力を向上させるためには、五郎島金時のように品質を担保する仕組みがあって然るべきだと思います」
新たな価値を生み出す数々の取り組み。その原動力は「れんこんを手にするお客さんに喜んでもらえるように」という変わらぬ気持ちだ。「それをないがしろにしたら、僕自身が楽しくないですから」。そういって笑顔をみせる川端さんは、すでに次なる「楽しいこと」を見据えているようだった。