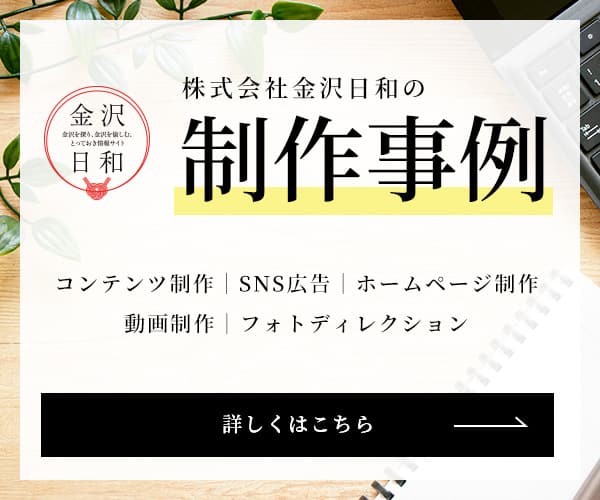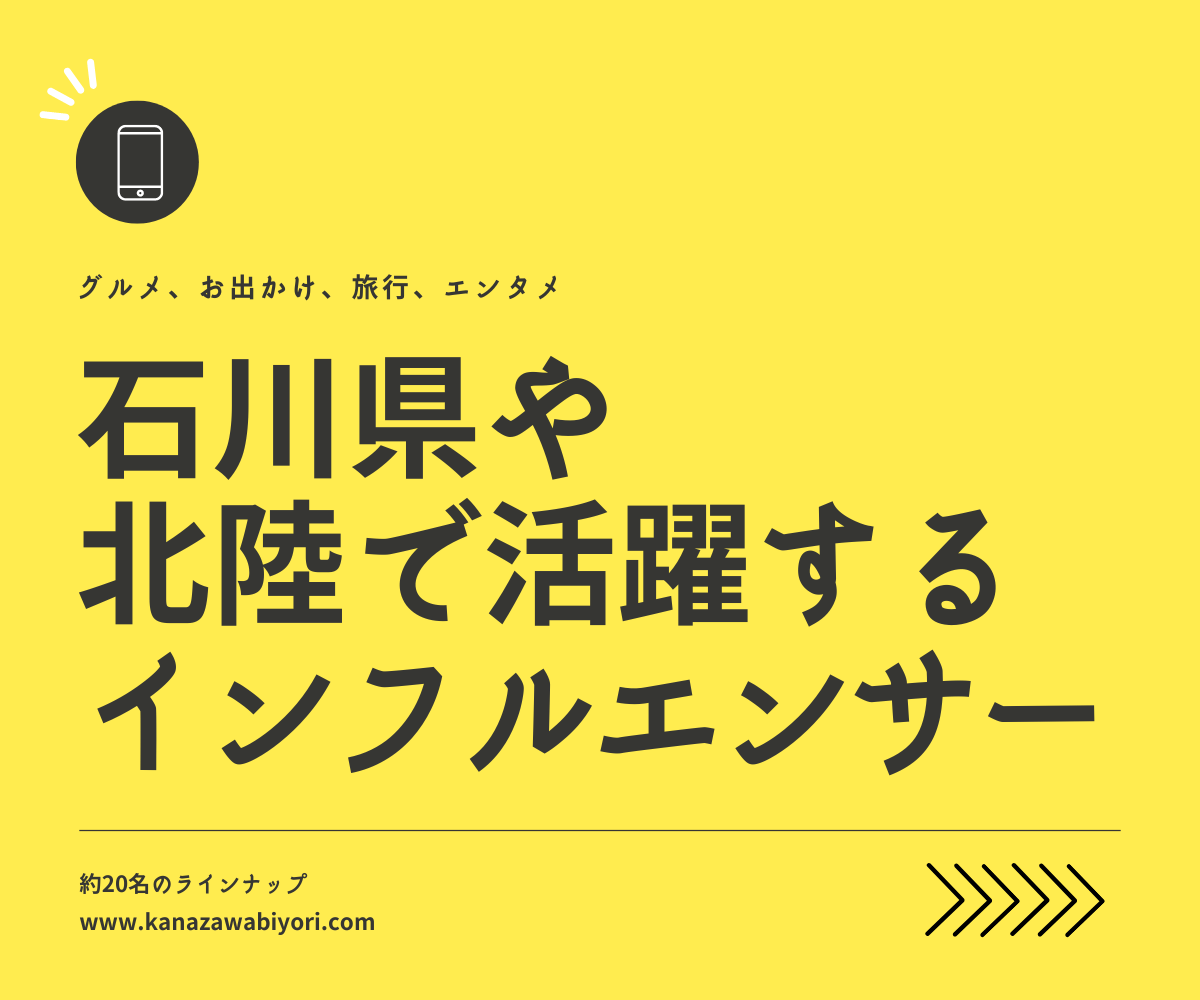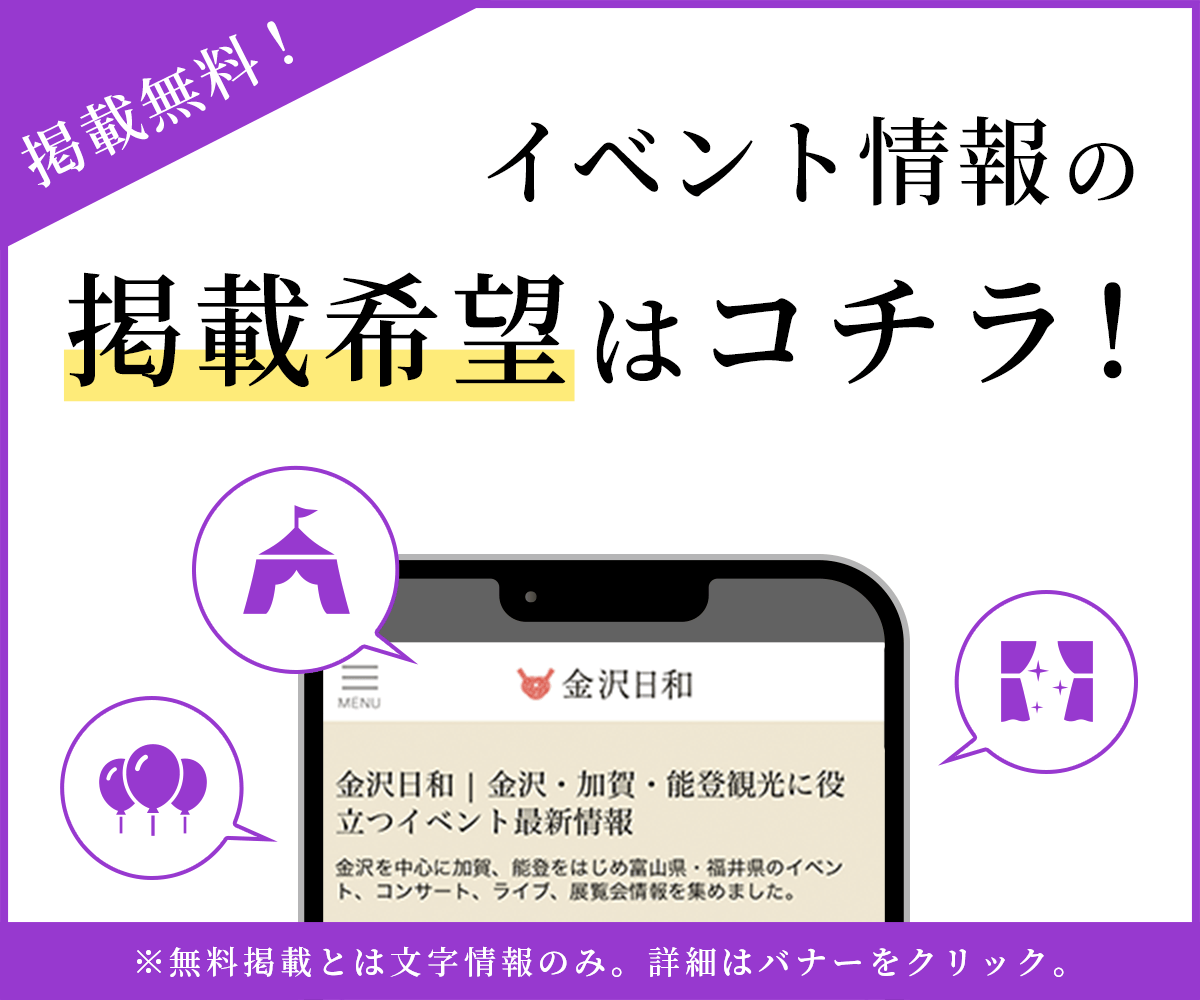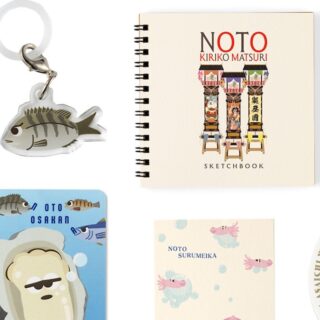山中座の天井絵
2015年4月9日(木) | テーマ/金沢の雑学

粟津、片山津、山代、山中。金沢から車で約1時間のこれらの温泉地を総称して加賀温泉郷と呼びますが、そのうち、豊かな自然と文化が残る、かの松尾芭蕉も愛した温泉地が山中温泉。その観光拠点といえる『山中座』に描かれているのが、今回ご紹介する天井絵です。
70m2の大きなキャンバスに描かれているのは、当地最大のイベント「こいこい祭り」をモチーフにしたもの。全国的にも有名な山中漆器の伝統的な技法(金や銀、色漆で仕上げる蒔絵の研ぎだし技法)によって生まれた作品は、ダイナミックかつ勇壮で、そのロビーにて華やかに観光客を出迎えてくれます。
ちなみに、対になっているのは「お椀」と「獅子」のみこし。天井絵では、そのタイトル「わらべたちのまつり」の通り、子供たちがみこしを担いでいますが、元々は「お椀」のみこしを漆器職人たちが、「獅子」のみこしを芸妓さんたちが担いでいたのだとか。その由来には、芸妓を獅子と呼んだことがあげられ、芸妓にはそれぞれ置屋があって、そこから旅館に通うのを忍び、風呂敷を被ったかたちが獅子舞の姿に似ていたから、との理由があるそうです。
そして、この『山中座』に行ったなら、もう一つ、ぜひ見ていただきたいのが大ホール。丁寧に塗られた漆はもちろん、意匠を凝らされたデザイン、山中温泉縁起絵巻の入浴場面を266色の色糸で表現した緞帳など、その空間自体が見事な芸術作品となっています。
聞くところによると、この『山中座』の建築には、なんと漆器職人のべ2,000人の匠の力が結集しているのだとか。自分たちの街の「誇り」をかけて、その細部にいたるまで、実直で丁寧な仕事が為されているからこそ、その美しさがどっと押し寄せるように感じられるのですね。
観光によって、私たちが心を動かされるのは、土地特有の自然や風土、暮らしに根差した文化、そして、その土地に生きてきた人たちの「思い」です。山中温泉に行く機会がありましたら、そんな熱い「思い」がぎゅっと凝縮した『山中座』にぜひ足をお運び下さい。かなりおすすめです。
写真提供:石川県観光連盟
その他の同じテーマ記事
【金沢の雑学・商店街編】火除地(ひよけち)とするために植えられた柿の木が由来!?『柿木畠振興会』
火事が多かった江戸時代、防火用の空地「火除地(ひよけち)」として植えられた柿の木が、この町名の由来と(続きを読む)
【金沢の雑学・商店街編】約400年もの歴史を誇る中心街の一つ『竪町商店街振興組合』
竪町は金沢で約400年もの歴史を誇る中心街の一つ。全長430メートルの中央通りは「タテマチストリート(続きを読む)
【金沢の雑学・商店街編】古さと新しさが調和した不思議な魅力を持つ『新竪町商店街』
レトロな雰囲気が漂う「新竪町商店街」。ここには骨董古美術品や異彩を放つギャラリー、若者に人気のこだわ(続きを読む)
【金沢の雑学・商店街編】昭和の風情が残るレトロな外観の建物が立ち並ぶ『尾山神社前商店街』
加賀藩祖・前田利家公と正室おまつの方を祀る尾山神社。そのお膝元にある「尾山神社前商店街」は開設70余(続きを読む)
【金沢の雑学・商店街編】日本三大名園の一つ・兼六園周辺で観光客をもてなす『金沢城兼六園商店会』
国の特別名勝に指定され、日本三大名園としても知られている兼六園。「金沢城兼六園商店会」は、そんな兼六(続きを読む)
【金沢の雑学・商店街編】街の歴史を知る老舗と、若き経営者の店が混在する『新天地商店街振興組合』
複合商業施設『片町きらら』の裏通りに位置し、片町繁華街の活況の一翼を担う「新天地商店街」。商店街設立(続きを読む)
【金沢の雑学・商店街編】金沢城の石垣を築くための戸室石を引いた道筋が町名の由来『石引商店街振興組合』
加賀藩との歴史が深く、江戸時代初期に金沢城の石垣を築くための戸室石を引いた道筋であったことが町名「石(続きを読む)
【金沢の雑学・商店街編】老舗から飲食店まで様々な業種が軒を連ねる『片町商店街振興組合』
昼はショッピングを、夜は遅くまで飲食を楽しめる北陸有数の繁華街「片町」。最新のトレンドショップや、金(続きを読む)
【金沢の雑学・商店街編】金沢市内で有数なオフィス街『南町通り商工会』
尾山八町の一つである南町は、400年以上前の藩政期以前に形成された、金沢でも最も古い町のひとつです。(続きを読む)
【金沢の雑学・商店街編】日本海側有数のショッピングゾーンとして知られる『香林坊(こうりんぼう)商店街』
江戸時代にはすでに商店街があった香林坊。明治時代、近くに「旧制第四高等学校」が開校したことから、学生(続きを読む)