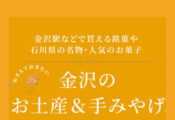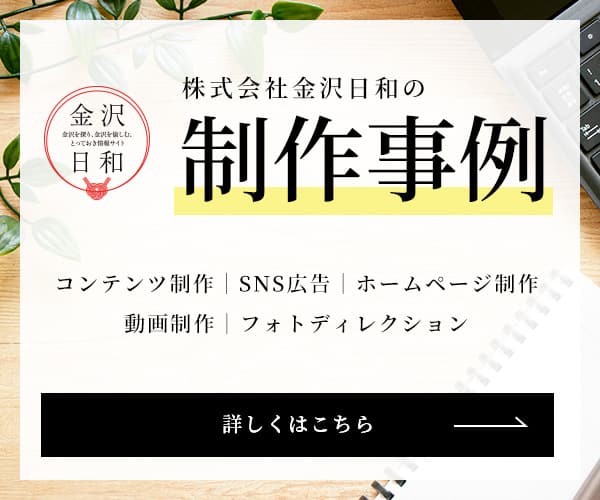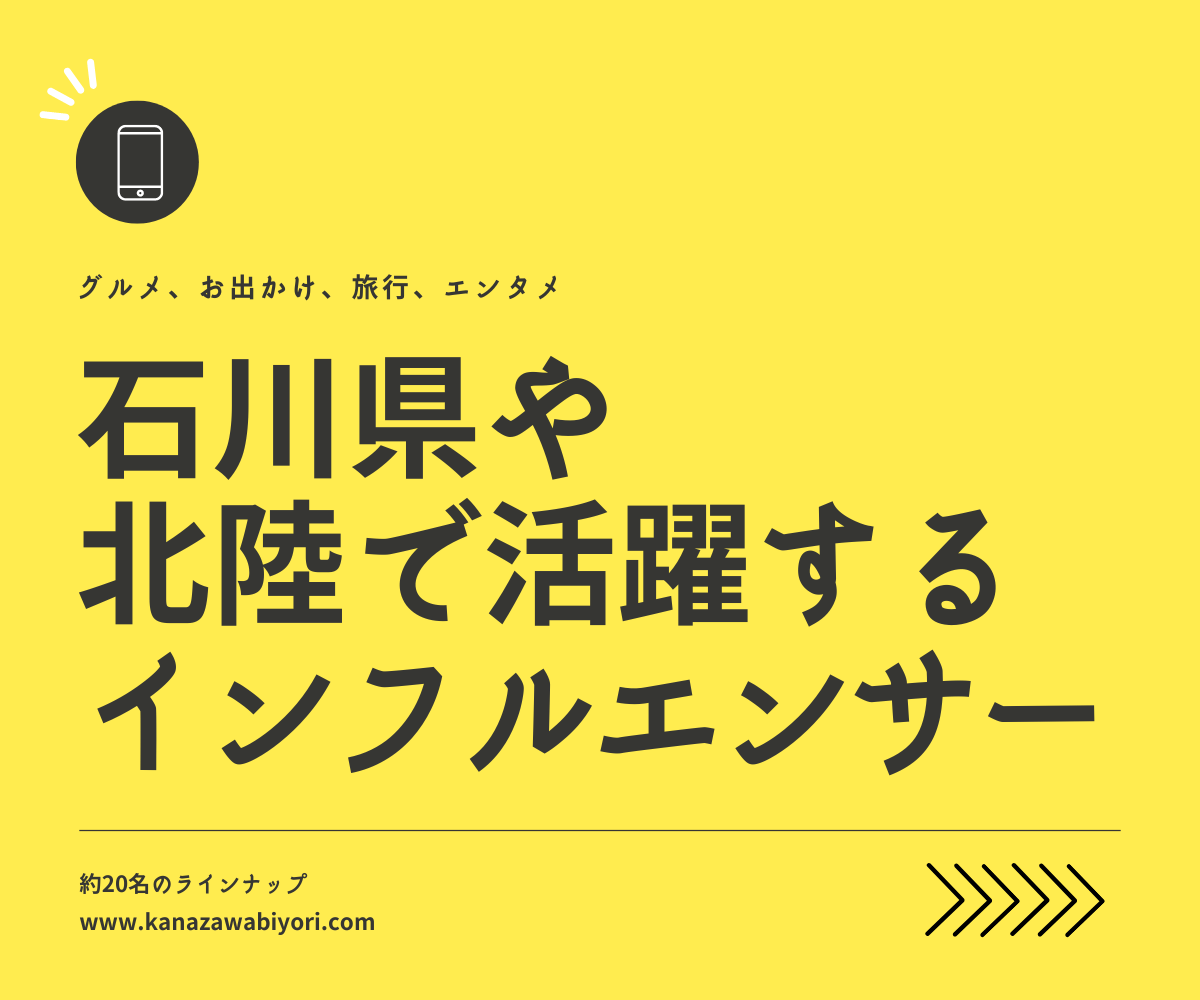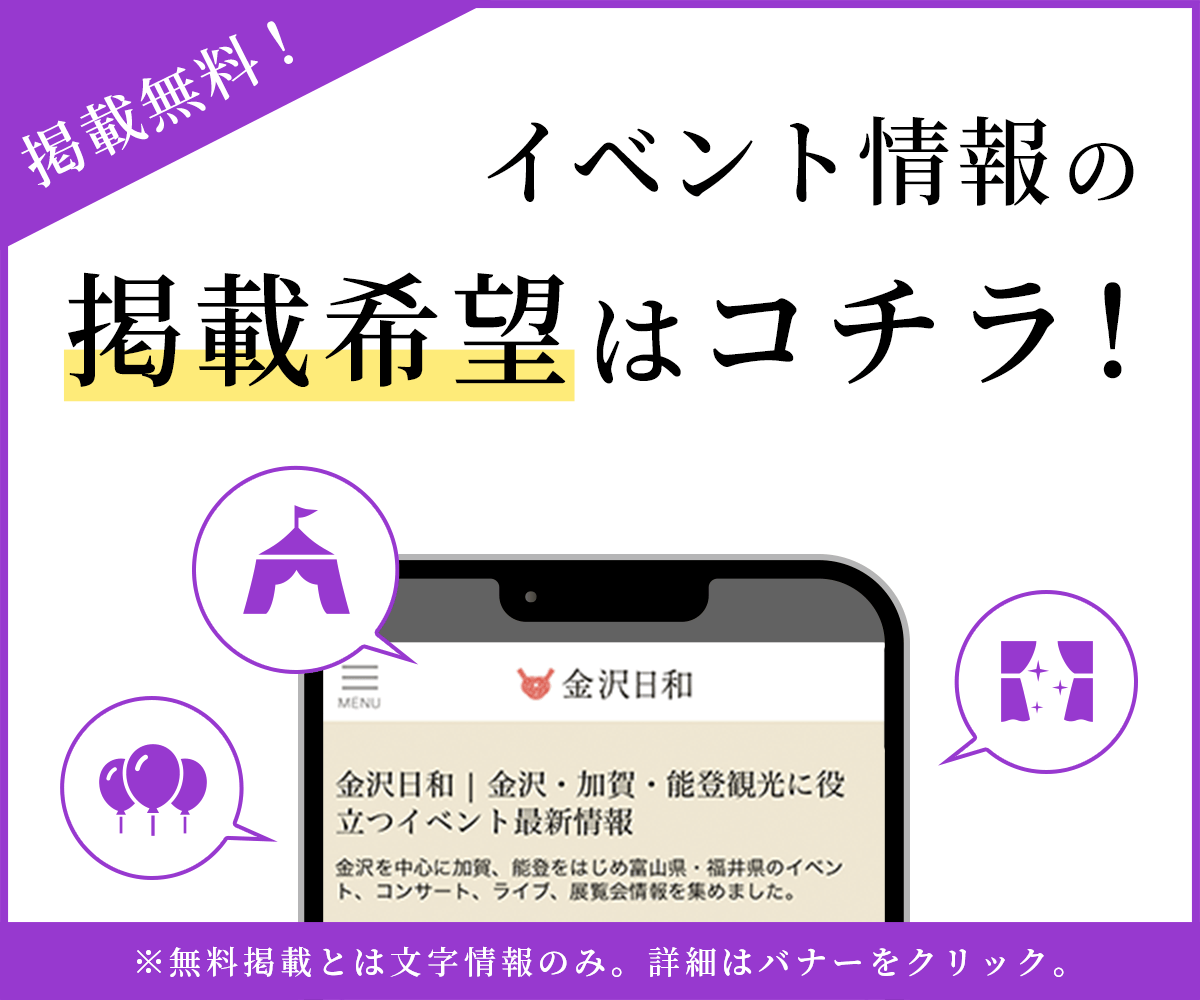能登のころ柿
2014年12月18日(木) | テーマ/金沢の雑学

昨年、ユネスコの無形文化遺産に登録された「和食」。その対象が「和食そのもの」ではなく「食に関する社会的習慣としての和食」にあることを知り、得心した記憶があります。例えば、おせち料理。少しややこしい話ですが、ユネスコが登録したのは「おせち料理」ではなく「お正月におせちという特別な料理を食べる習わし」だったんですね。同じように無形文化遺産に登録されているフランス料理も、メキシコ料理も、地中海料理も、その料理自体が登録されたのではなく、その食をめぐる文化が登録されているのだそうです。
そんな文化としての食で、忘れてならないのが「郷土食」です。現在のように流通が発達していなかった時代、限られた食材を最大限に活かそうと、その土地土地の気候や風土に合わせて考えられた食品は、まさしく先人たちの創意と工夫そのもの。石川県にも「郷土食」と呼ばれるものが沢山ありますが、今回ご紹介したいのが、能登半島の中ほどに位置する志賀町特産の「ころ柿」です。
この「ころ柿」、いわゆる「干し柿」のことですが、能登の「ころ柿」の場合、その材料として95%を占めているのが「最勝」という渋柿。その渋柿を、ひとつ一つ丁寧に、皮をむき、糸をくくり、乾燥させ、手もみすることで、やわらかく上品な甘さをもったころ柿に仕上げていきます。渋いからといって破棄するのではなく、干すことによって糖度を上げ、食材が少なくなる冬の保存食に。干し柿の甘みは甘柿の約4倍にもなり、水分が抜けることで食物繊維の含有率が高まり、コレステロールを吸収して排出してもくれるんだとか。昔ながらの天然の保存健康食品。こうした知恵こそ、まさに文化だよなぁと思うのです。
山里に点在する集落の家々に橙色の柿の実が干されるのは11月頃。晩秋から初冬にかけての静寂な山里と同化する風景には、なんともいえない郷愁と美しさがあります。今年の出荷もすでに終盤にかかっていますが、お正月の贈答品に購入して、大切な方たちと、そんな風景を思い浮かべながら食してみてはいかがでしょうか。
有名な観光名所もいいのですが、県外の方で、もし能登に行かれる機会があって、お時間があるのであれば、ぜひレンタカーを借りて、目的地を決めず、旧道をゆっくりドライブされることをおすすめします。今の日本に失われつつある、こんな気候・風土・歴史に根ざした文化が、まだまだ沢山、色濃く残っていますので。
写真提供:石川県観光連盟
その他の同じテーマ記事
【金沢のお正月】福徳せんべい
2024年もあとわずか。イベントを一つひとつ終え、お正月準備も万全という方も多いのではないでしょうか(続きを読む)
【金沢のお正月】全国的に珍しい石川県の「紅白」鏡餅。
石川県民の多くは紅白の鏡餅を飾ります。そんなの当たり前でしょと思った県民の皆さん、実は全国的には上下(続きを読む)
【金沢のお正月】金沢のお正月に欠かせない祝菓「福梅(ふくうめ)」
12月になると、金沢近郊の和菓子店には正月の和菓子「福梅(ふくうめ)」が並びます。 毎年決まった店(続きを読む)
【金沢のお正月】金沢の正月に欠かせない占い系縁起菓子「辻占(つじうら)」
(写真提供:金沢市) 金沢のお正月にいただく和菓子の代表・福梅(ふくうめ)と並んで有名なのが「辻(続きを読む)
金沢のお雑煮、ルーツは名古屋!? 石川県のお雑煮のあれこれ【金沢トリビア】
もうすぐお正月。今回はお正月に欠かせない「お雑煮」についてのトリビアです。 お雑煮と聞くとねじり梅(続きを読む)
豚汁をめった汁と呼ぶのは石川県民だけって、知ってました?【金沢トリビア】
豚肉やニンジン、大根、ネギ、ゴボウなどの野菜がたっぷりはいった味噌汁を、何と呼びますか? 「めった(続きを読む)
金沢のお土産&手みやげ 番外編|手みやげのマナー
ご挨拶に伺う機会が増える時期ですね。「今年もお世話になりました」、「新しい一年もよろしくお願いいたし(続きを読む)
【金沢の雑学・商店街編】老舗から飲食店まで様々な業種が軒を連ねる「片町商店街振興組合」
昼はショッピングを、夜は遅くまで飲食を楽しめる北陸有数の繁華街「片町」。最新のトレンドショップや、金(続きを読む)
【金沢の雑学・商店街編】昭和の風情が残るレトロな外観の建物が立ち並ぶ「尾山神社前商店街」
加賀藩祖・前田利家公と正室おまつの方を祀る尾山神社。そのお膝元にある「尾山神社前商店街」は開設70余(続きを読む)
【金沢の雑学・商店街編】金沢市内で有数なオフィス街。『南町通り商工会』
尾山八町の一つである南町は、400年以上前の藩政期以前に形成された、金沢でも最も古い町のひとつです。(続きを読む)